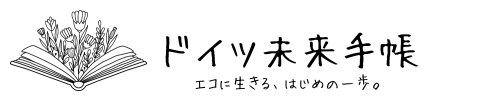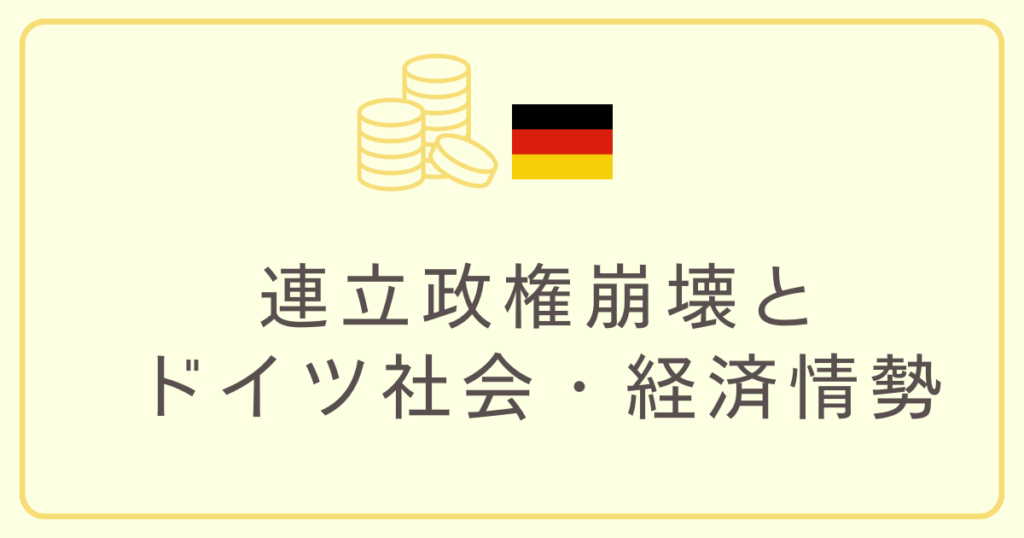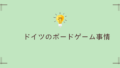日本でもその年の流行語大賞が発表されるが、ドイツにも「今年のフレーズ」(Wort des Jahres) なるものが存在する。2024年は、Ampel-Ausである。経済政策の財源確保を巡る連立政権内の対立から生じたリントナー財務大臣の罷免、FDPの政権離脱に伴う連立政権の崩壊を意味している。それほどにも、今回の政権崩壊はドイツ社会を揺るがしており、先行きの不透明感に拍車をかけている。日々の生活や仕事を通じて感じることも含めて、この記事で最近のドイツの社会・経済情勢をお伝えしたい。
債務ブレーキに関する議論
まず、今回の財源確保を巡る議論においては、ドイツにおける「債務ブレーキ」なるものが鍵となる。ドイツの憲法にあたるドイツ基本法において、国家の債務はGDPの0.35%を上回ってはならないとの規定がある。これは、憲法上の規定なので、遵守しなければならない。
しかし、ここ数年、コロナ危機、ウクライナ危機、これらに端を発するエネルギー価格の高騰といった一連の危機への対応によって、ドイツ政府の歳出は年々増加しており、債務ブレーキを緩めなければ、必要な政策が実行できない状況に陥っていた。
そもそも、コロナ危機の発生時、当時のメルケル政権がパンデミックへの対応として2400億€の緊急予算を計上。当時は緊急事態であったため、債務ブレーキの適用除外が認められた。このうち、未使用であった600億€を現政権が気候変動対策のために使用するとして、議会に提案、可決された。しかし、2023年の連邦憲法裁判所の判決により、コロナ対策で計上した予算を気候変動政策に使用することは違憲である、との判断が下されてしまう。これによって、600億€で賄うはずであった各種政策の実施が危ぶまれる事態となった。
ハーベック経済大臣(緑の党)は、経済の活性化のために、債務ブレーキを凍結しても、企業の投資を補助する補助金政策の実施を求め、これに対してリントナー財務大臣は、債務ブレーキの遵守のためにはこれ以上の歳出は認められないとして、これを拒否。これを受けて、ショルツ首相はリントナー財務大臣を罷免、同大臣率いる自由民主党(FDP)は政権から脱退し、ドイツの連立政権が事実上崩壊する形となった。
現政権の経済政策への批判
そもそも、政権発足時から、根本的な政策路線が異なる3党が政権を率いることができるのかという疑問があった。また、それらが政策の決定・実施の遅延に繋がることも多々あり、特に経済界からは不満の声が高まっていた。また、ハーベック経済大臣の経済政策が、ドイツの競争力低下を招いているという批判も特に経済界から上がっていた。これまでの批判の主な論点は、以下のようにまとめられる。
- 高騰するエネルギー価格に対して、これといった打開策が出されていない。多くの企業が生産拠点をドイツから他国に移している。
- 多額の補助金を使って企業の投資を支援しようとしているが、非効率かつ市場を歪めているとの批判。ドイツで大手企業はかなりの割合の補助を政府から受けており、それが非効率的な経営や成長を阻害しているのではないか、という印象を受ける。
- 官僚主義を撤廃すると宣言しながら、サプライチェーン法など新たな官僚主義的負担を企業に追わせている。
成長の兆しが見えないドイツ経済
正直なところ、ドイツ経済が成長する兆しが全く見えない。ドイツの主要な経済研究所は、2024年12月に冬季予測を発表し、これによると2025年の経済成長は0.8%から0.3%に下方修正されている。国内の生産能力の低下や貿易の伸び悩みなど、理由は多岐に亘るとは思うのだが、ここではあくまで一住民としてドイツで住む立場から、最近の経済・社会の問題点について考えてみたい。
国によって企業文化も異なるとは思うが、ドイツはあまりにも補助金頼みの企業が多すぎる印象を受ける。つまり、経営を効率化せずとも、生き残れてしまうのである。例として挙げられるのは、ドイツの百貨店Galeria Kaufhofである。2020年7月に破産申請手続きを行い、コロナ禍のロックダウンで売上に影響が出たとして、政府の補助を受けていた。2022年に更なる補助金を申請、2023年には2回目の破産申請、2024年1月に3度目の破産申請手続きを行っている。
3回も破産申請をする前に打つ手はなかったのだろうか、と非常に不思議に思うと同時に、公的資金を注入してまで一百貨店を維持する必要性がイマイチ理解できない、というのが正直な感想だ。確かに、破産によって、多くの雇用が失われることは、社会にとって大きな打撃かもしれない。
ただ、自由経済である以上、企業の繁栄・衰退は自然の営みとして受け入れられるべきであるし、被雇用者もそのことを頭に入れて生活しなければならない。政府が事あるごとに介入していては、いくら税金を増やしても、歳入が足りなくなるだろう。
そして、もうひとつ、ドイツ経済の未来を見据える上で懸念されるのは人材である。専門性を有する人の割合は恐らく日本よりもドイツの方が高いと思うのだが、とにかく働かない人が多すぎる、というのがドイツに住んでいて感じることだ。
労働者の権利が確保されているのは良いことではあるのだが、時にそれが濫用されていることがある。人件費が高い、不満不平が多い(権利の主張は重要だが、時と場合によると思う)、病欠の数が多い。企業にとってこのような人材はリスクとなり、エネルギー価格の高騰とともに人材のリスクもドイツへの投資を控える動きへとつながるのではないかと懸念されている。
米国も、EU諸国も債務が年々増えている。これによって、更なるインフレの懸念が高まっており、2025年のインフレ率はドイツや米で3%を越える恐れも出ている。まさに出口の見えないトンネルを歩んでいるような状況で、巷でも、生活が苦しくなり、今後の経済の先行き不安を案ずる声が上がっている。
政策バランスの難しさ
ただ、債務ブレーキによって必要な政策が滞ってしまうというのも、問題ではある。例えばコロナ危機においては、休業補償、ワクチンの確保・インフラの確立など、世界の誰もが予想していなかった事態であるとともに、国民の命を守るために必要な歳出であるというのは明確であろう。
では、ウクライナ危機やエネルギー危機はどうなのであろうか?経済政策は?債務ブレーキの緩和をするのであれば、何を基準にどこで線引きをするのか、非常に難しい判断が求められる。
また、経済危機に陥った際に、誰をどこまで支援するのか、というのも難しい問題である。現政権がこれまでの求職者支援(ハルツVI)を市民手当(Bürgergeld)に刷新し、給付額を引き上げた際にも、多くの国民の労働意欲を損なうものであるとして批判が巻き起こった。働かなくても、市民手当でそれなりの生活ができてしまうので、長期間失業しても焦ることなく、給付を受け続けている人が続出しているようだ。日本では、到底考えられない。

私の知り合いにも、市民手当もらえるし、そんなに急いで転職活動しなくていいかなと思ってる、と躊躇いもなく言っている人がいて、かなり驚きました。
結局、政治が物事を判断する基準となるのは、その国の国民の考え、国民の意思であろう。2月末の前倒し総選挙がどういう結果になるのか、そして、今後のドイツの社会がどのような方向に向かっていくのか、ドイツに住む一外国人として注目している。