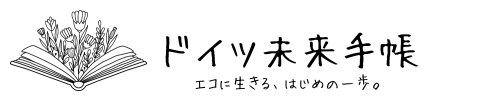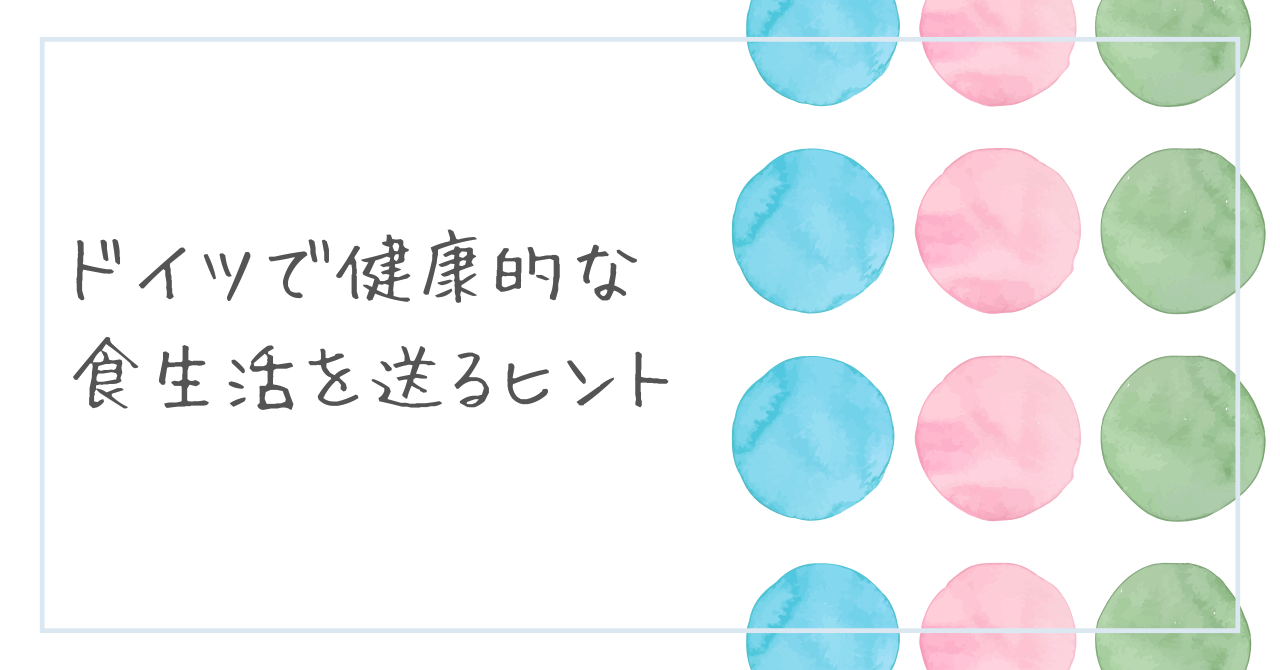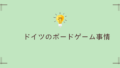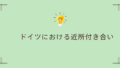ドイツに再移住してから早5年。数年前から、どうも消化器官の調子が優れず、何となく不調という状況が続いていた。病気では全くなく、いわゆる不定愁訴というものだろう。日本に帰ると元気一杯になるのに、ドイツに戻ると身体が重い、疲れが取れない、ということが頻繁にあった。

特にドイツの冬は天気も悪く、日照時間も短いので、そのせいかな?と思ってました。
たまたま、東洋医学(ドイツではTraditionelle Chinesiche Medizin、略してTCM)の良い先生に出会い、食生活へのアドバイスも含めて針治療をしてもらっている。これによって、症状がかなり改善した。色々と食生活へのアプローチをする中で見えてきたことがあるので、参考までにまとめていきたい。それぞれ体質が異なるので、私に合うものが、他の人にも合うかは分からない。ただ、同じような症状に悩まされている日本人が私の周りだけでも何人かいたので、体質改善のヒントとなれば幸いである。
グルテン・乳製品を含む食品
ドイツと言えばドイツパンを思い浮かべる人も多いだろう。街角でも美味しそうなパンが並べられていて、黒パンから菓子パン、クロワッサン、ケーキなど、バリエーションも豊富だ。私も最初の頃は、ドイツの黒パンを朝ご飯に食べていたし、出張などで遠出するときのお昼は大体パン屋さんで売っているサンドイッチなどを購入していた。

しかし、ある時から、グルテンを含む食品を口にすると、お腹の調子が悪くなることが多くなった。東洋医学的には小麦を使った食品は身体を冷やすため、冷え性の私はあまり多く摂取するべきではないそうだ。
それ以来、朝食にはグルテンフリーの穀物を使った御粥(ポリッジ)を食べるようにしている。また、昼食・夕食は米又はジャガイモを主食にするように。これによって、私の胃腸の調子は劇的に改善した。今ではパンを食べたいという欲求はほとんどない。
最近ではグルテン不耐症の人も増えていることから、グルテンフリーのパスタなどもスーパーで売られているので、非常に助かっている。私の場合は、乳製品も体調不良の原因だったようで、牛乳、ヨーグルト、生クリーム、チーズなど、できる限り減量し、植物性ミルク(豆乳など)にシフトした。豆乳、アーモンドミルク、ココナッツミルクなど、種類も豊富だ。ただ、添加物や砂糖を使ったものも多く出回っているので、注意が必要だ。子どもの頃から、乳製品を摂取しないとカルシウム不足になる、という教えが頭の中にこびりついていた私にとっては、乳製品を減らすことに抵抗があった。やってみると自分の体質に合っていたようで、以前より快適に過ごせるようになったのが嬉しい。
食材の性質に注意する
薬膳においては、食材の性質を寒・平・温に分けて考える。私の場合、冷え体質なので、寒性の食材は避けるのがベター。バナナ、きゅうり、トマト、緑茶などがこれに該当する。逆に、根菜類、ジャガイモ、かぼちゃなどは身体を温めてくれる効果がある。食材の調理方法にも注意が必要だ。サラダやスムージーは健康にいいと巷では言われているが、冷え性の人は控えるのが賢明だ。私も生野菜やスムージーを大量に摂取すると、大体お腹が痛くなる。ゆるっと薬膳に取り組みたい人には、こちらの本がおすすめ。簡単に薬膳の要素を取り入れられるレシピやヒントを紹介している。
TCMの先生には、食事に汁物を取り入れるように、とアドバイスされたので、なるべくお味噌汁や根菜入りのポトフなどを作るようにした。そして、一汁一菜でもOKと考えるようにした。土井善晴さんの「一汁一菜でよいという提案」は、日本人としての食事のあり方や楽しみを改めて考えさせる内容の本で、お気に入りの一冊だ。

加工食品はなるべく控える
これは、どの食生活アドバイザーに聞いても言われること。加工食品は百害あって一利なし。特にドイツの加工食品は味も濃いし、美味しいとは言えないものも多い。私は特に敏感なので、外食や加工食品の食事が続くと、大体胃腸がしんどくなる。手間暇はかかるが、可能な限り自分で材料を調理する方が経済的だし、結果として美味しく味わえる。困ったことに、ドイツのレストランでは、味付けやソースに加工品が使われていることがとても多く、素材の味をそのまま楽しめるようなお店はとても少ない。そのため、お金を出しても何となく満足できない場合が多く(少なくとも私の場合は)、ここ最近は外食することもめっきり減ってしまった。恐らく、インフレの影響で外食業界もコスト削減を迫られており、なるべく値段の安い材料を仕入れる必要が出てきているのだろう。自炊の場合、高級な食材を購入しても、1週間の食費はたかが知れている。食いしん坊の私にとっては、外食の機会が減って残念ではあるが、日本に帰国した際に、美味しいものを堪能することを楽しみにしている。
可能な限り有機食品を購入
はっきりとした効果は分からないが、なるべく農薬を使用していない野菜・果物、そして、有機飼料で育てられた家畜(或いは自然に近い飼育法で育てられた家畜)を食べるようにアドバイスを受けた。確かに、好んで環境負荷の高い食品を食べる必要もないので、少々割高ではあるが、有機食品を購入するようにしている。特に南ドイツは農業・蓄産業が盛んであるため、地元の美味しい有機野菜が多く並べられている。すべての食材を無農薬でそろえることは難しいし、ストイックになりすぎてもよくないので、ほどほどで良いかなと自分では思っている。地元産業への支援も兼ねて、なるべく南ドイツ産のものを選ぶようにしている。ちなみに、ビオではないが、ミュンヘンから南に50Km離れたTegernseeと呼ばれる地域では和牛(その名もTegyu)が飼育されている。直接、農家から購入することもできるので、ご関心のある方は是非行ってみて欲しい。


日本の和牛とは少し食感が異なりますが、Tegyuもとても美味しかったので、かなりおすすめです!
1日30品目の呪い
私が目からウロコだったのが、1日30品目を目指して種類を多く食べなくても良い、というアドバイスをもらったこと。私達日本人は、子供の時から、満遍なく食べることを教わり、巷でも1日30品目食べると健康に良いというフレーズはよく聞く。私もドイツに来た当初は、いかに一日の中でバラエティに富んだ食事を作るか、ということに頭を巡らせていた。そして、野菜や果物の種類が圧倒的に少なく、魚もあまり手に入らない国で絶望的な気分になっていた。
しかし、体質的に消化できないものをいくら食べても効果はない。
そうだとすれば、自分の体質に合ったものを、いつもより少し多めに摂取することの方が、栄養バランス的には良いように思える。品目数の呪いから解放されたことで、日々の食生活のプランが大分楽になった。
ちなみに、TCMの先生は、タンパク質の呪いからも私を解放してくれた。テレビやネットなどでは、タンパク質不足がテーマとして頻繁にとりあげられている。あまりタンパク質(特に肉類)を増やしすぎると消化不良に悩まされるということを相談したところ、植物性タンパク質(豆腐や豆類、ナッツ類)で補充したり、少量のお肉を回数を分けて食べることで全く問題ないとアドバイスを受けた。
完全菜食主義者の人は注意が必要だが、そうでない限り、あまり気にしすぎる必要はなさそうだ。何より、楽しく美味しく食べることが一番だと思う。それから、ゆっくり座って3食食べる、ということも重要だそうだ。忙しいとお昼は適当に済ませてしまったり、仕事をしながら食べる人も多いと思う。30分で良いので仕事から離れて、食事に集中することで消化も促進されるようだ。
一番大事なのは自分の身体の声を聴くこと
これまでの食養生で学んだことは、自分の身体の声を聴いてあげるということ。世間一般に言われる「身体に良いこと」を真似するのではなく、自分の身体に合った食品・調理方法を見つけ出していくことが重要だ。私は食べることが大好き。でも、ドイツでは重なる体調不良から食べることが嫌になってしまい、それがストレスとなっていった。そんな私を救ってくれたTCMの先生には本当に感謝しているし、この記事が少しでも同じ境遇の人を救うヒントとなることを願っている。