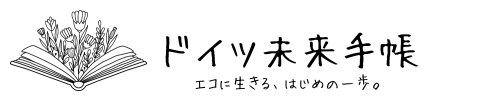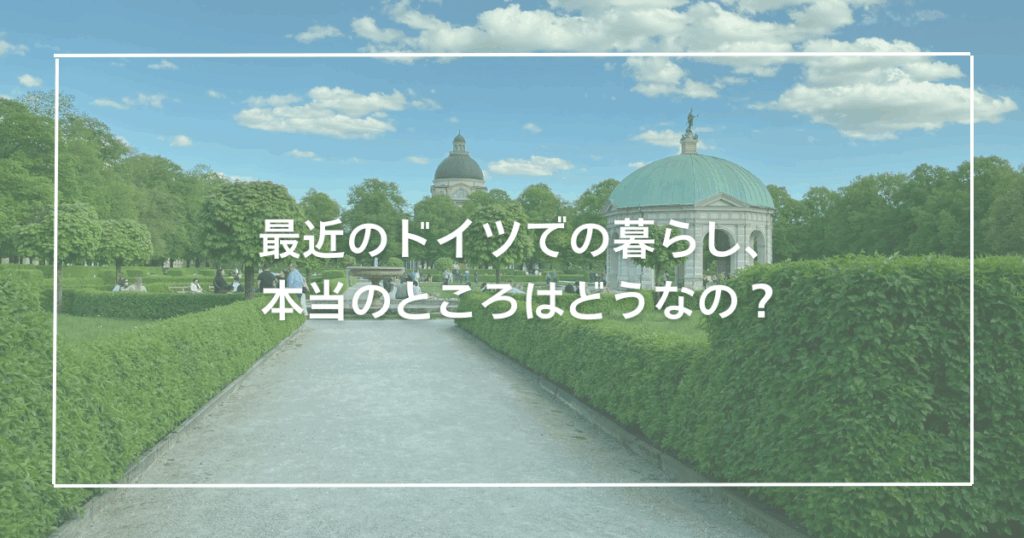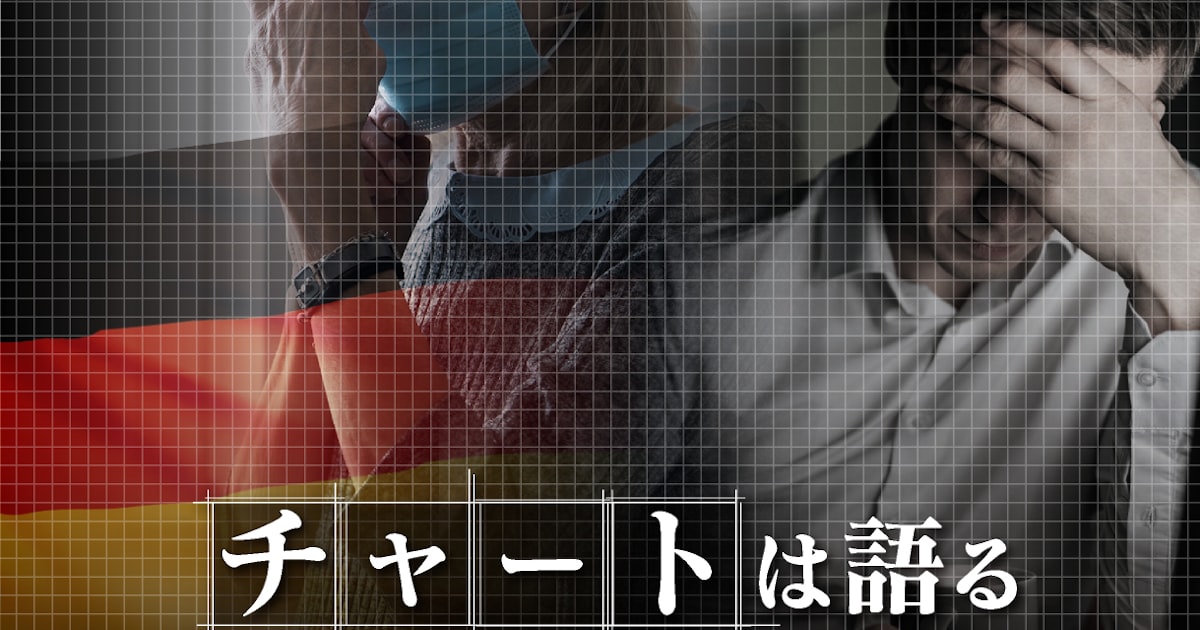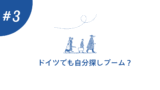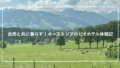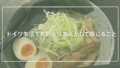近年、日本の新聞では「ドイツ経済の凋落」「かすむ経済効率」「製造大国の危機」といった厳しい経済状況を伝える記事を目にする機会が増えている。実際に現地で暮らしていると、現地の住民としての肌感覚はどうなのかと思われる方も多いことだろう。
本稿では、筆者の個人的な見解と生活の中での実感をもとに、現在のドイツの様子をお伝えしたい。
国民の生活は苦しくなる一方
まず、一般的な感覚として、現在の経済状況は芳しくない。ドイツの大企業は相次いでリストラ策を発表しており、ウクライナ危機以降に始まったインフレの影響も国民生活に深刻な影を落としている。給与はインフレ率ほどには上昇しておらず、必然的に多くの国民が生活の中で我慢を強いられているのが実情である。
これはあくまで直感的な印象ではあるが、街全体の雰囲気もどこか沈んでいるように感じられる。もともとドイツ人は、どちらかと言えば悲観的な気質を持つ国民であると言われている。「元気?(Wie geht’s?)」と尋ねられても、たとえ体調が良くても「悪くないね(Nicht schlecht)」と答えるのが一般的である。
そうした元来のメンタリティに、昨今の不安定な経済状況が拍車をかけ、全体的に暗い空気が漂っている。 南ドイツは比較的裕福であり、雰囲気も明るくおおらかであるが、それでも厳しい状況があることに変わりはない。

実際に、先日ミュンヘンで知り合った50代のドイツ人女性は、「年金だけではドイツで生活していくのが難しいので、今から海外への移住を検討している」と語っていた。将来、自国で暮らすという選択肢を諦めざるを得ないという事実は、現在の経済情勢の厳しさを象徴しているように思われる。
鰻上りの家賃、外食産業も値上げせざるを得ない状況
また、家計をさらに圧迫している要因として、家賃の高騰が挙げられる。ドイツの大都市圏ではここ数年、家賃が急激に上昇している。Statistikaの統計によれば、家賃指数は1995年の71.8から、2024年には107.5にまで上昇している1。かつて「安く住める都市」として知られていたベルリンも、今ではミュンヘン、フランクフルトに続いて1平米あたりの単価が高い都市となっている2。
もともと家賃が高いことで有名なミュンヘンでは、シェアハウスでさえ月700〜800ユーロ(約10〜12万円)といった水準に達しており、庶民の生活を直撃している。


ちなみに、外食に関しても、値上げは顕著である。特に、電気代やガス代の高騰により、多くのレストランが経営難に陥っており、メニュー価格の上昇が相次いでいる。その結果、それほど美味しくない食事にも相応の価格が設定されるようになり、外食の満足度は低下する一方である。ドイツの国民的軽食であるケバブですら、現在の相場は7〜8ユーロに達している。
「この値段でこのクオリティであれば、わざわざ食べに行かなくてもいい」と感じる店も少なくない。 もともと筆者は外食の頻度が高い方ではなかったが、近年では誕生日などの特別な日を除き、ほとんど外で食事をすることがなくなってしまった。
日経新聞でもとりあげられた病欠問題
日経新聞でも取り上げられた病欠問題だが、ドイツでは、とにかく休みが多い。病気やケガの際にしっかりと休める制度が整っていることは良いことであるのだが、その一方で制度の悪用が少なくないという現実もある。
そして、心の病にかかる人も近年は急増している。
その原因について、考えられることをこちらの記事で紹介しているので、ご関心がある方はどうぞ。


ドイツ鉄道でも、病欠で人員が足りず、遅れの原因になることが多々あります。
病院で病欠証明書を受け取れば、その間の給与補償が医療保険から企業に対して支払われる仕組みとなっている。当然ながら医療保険の支出は膨れ上がり、ここ数年は保険料の引き上げが続いている。2024年の医療保険制度は62億ユーロの赤字となった3。
所得が上がるほど保険料も増え、加えて高い税率も適用されるため、昇給が必ずしも手取りの増加に結びつかず、結果としてキャリアアップに対する動機づけが弱くなるというジレンマがある。 こうした背景からか、労働への意欲は全体的に非常に低い印象を受ける。
休暇から戻ったばかりでも、すぐに次の休暇の予定を立て始める人が少なくない。
日本人の感覚からすれば、それほど忙しくない仕事であっても、「ストレスが多い」「疲れる」と口にする人が多く、「これでは経済成長は難しい。働く意志そのものが希薄なのだから」と感じざるを得ない。金曜日の午後など、ほぼ仕事をしている人はいない。
もちろん、業界によっても異なるであろうし、製造業のように長年ドイツの経済を支えてきた基幹産業においては、仕事のスタイルも異なるのかもしれない。
もっとも、これだけ働いていなくても経済成長を当然の如く望むというのはドイツ人にとってはごく自然な価値観であり、筆者のような外国人にとって違和感があっても、現地の人々にとっては違和感のない生活スタイルなようだ。このような価値観の差異には戸惑うこともあるが、一方で非常に興味深くも感じられる。
官僚主義の行き過ぎにより、進まない改革
もう一つ、現在のドイツ社会における大きな課題として、「デジタル化の著しい遅れ」が挙げられる。
行政手続きの多くは依然として紙と郵送を前提としており、オンラインで完結できるものは驚くほど少ない。たとえば住民登録の変更やビザ関連の申請など、日常的な手続きでさえ紙の申請書に記入し、窓口の予約を取って直接出向く必要がある。
イラク出身でドバイに長く住んでいた友人は、送付されてくる手紙の量が地味にストレス、と嘆いていた。ドバイでは多くの手続きが電子上で済むらしく、ドイツに来て書類用のファイルで本棚が埋め尽くされている、とぼやいていた。


日本もそれなりに紙文化なので、私はそこまでストレスに感じることはなかったのですが、確かに紙の量が半端ないかも、と気づいた瞬間でした(笑)
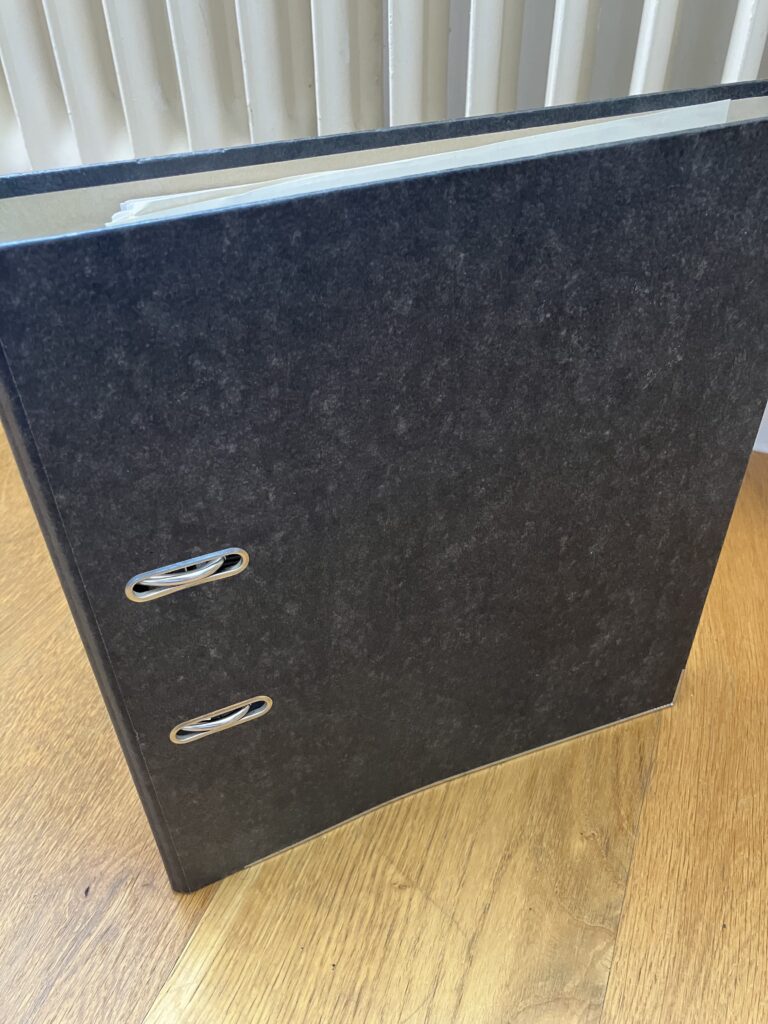
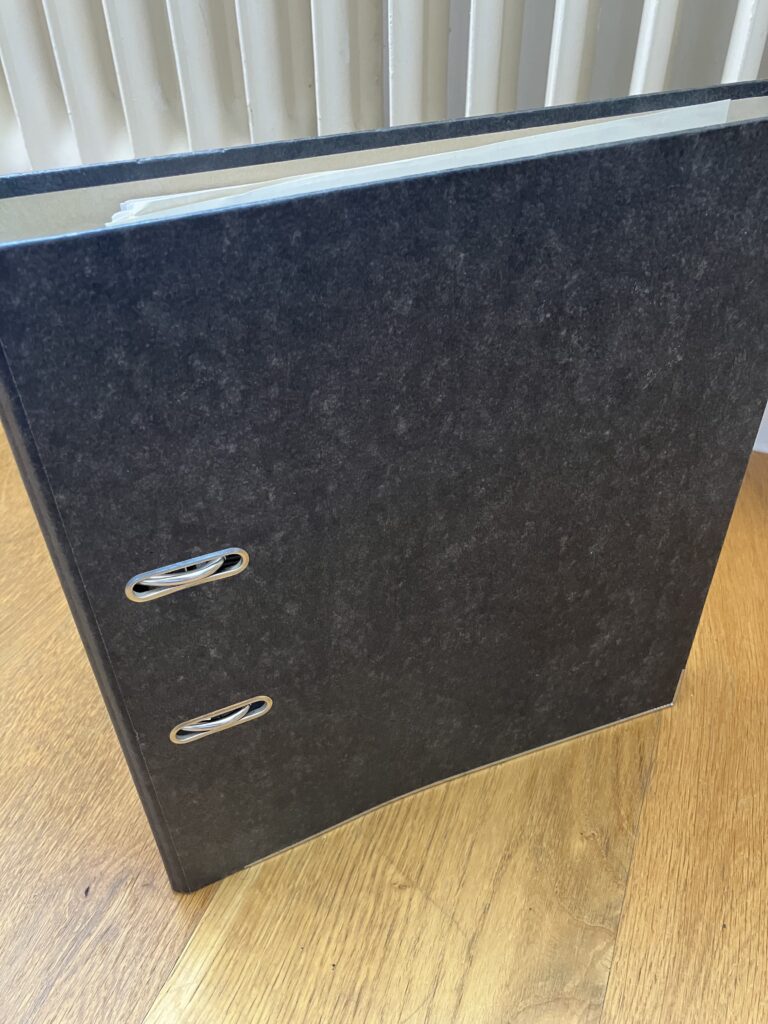
デジタル化が進まない背景には、ドイツ社会に根強く残る官僚主義がある。あらゆる手続き・ルールが煩雑で、何重にも承認や許可を求める構造が改革のブレーキとなっている。政府もこれらが経済成長を阻害する要因になっているとして本腰を入れて取り組む意向を示しているが、もはや問題が根深すぎて、どこから手をつけて良いのやら分からない状態だ。
まとめ:ドイツは住みやすいのか?
ドイツへの移住や留学を検討している方も多いと思われるが、現時点でのドイツは様々な課題を抱えており、「住みやすい国」とは言いがたいのが著者の個人的見解である。
もちろん、休暇が取りやすく、残業も少ないという意味では働きやすい国であるが、今後の成長が期待できる国かと問われると、楽観視するのは難しい。価値観は人それぞれなので、何を重視するかによって、ドイツの住みやすさに対する答えは変わってくると思う。
仕事に対するモチベーションが根本的に高くない人々と協働するには、相応の柔軟性と理解が求められる。生活環境としてのドイツには良い面も沢山あるのだが、現在は慎重な検討が必要な局面にあると思っている。一住人の意見として、今後、ドイツに移住を考えている人の参考になれば幸いである。
下記のドイツ情報ブログ⇩バナーをクリックして応援していただけると嬉しいです!
にほんブログ村
- https://de.statista.com/statistik/daten/studie/609521/umfrage/monatlicher-mietindex-fuer-deutschland/
↩︎ - https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1885/umfrage/mietpreise-in-den-groessten-staedten-deutschlands/ ↩︎
- https://www.aerzteblatt.de/news/krankenkassen-verbuchen-62-milliarden-euro-defizit-e5267d75-8065-4342-a993-80bdabd49a55 ↩︎