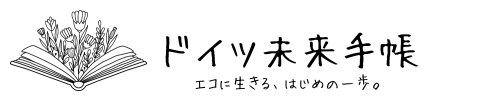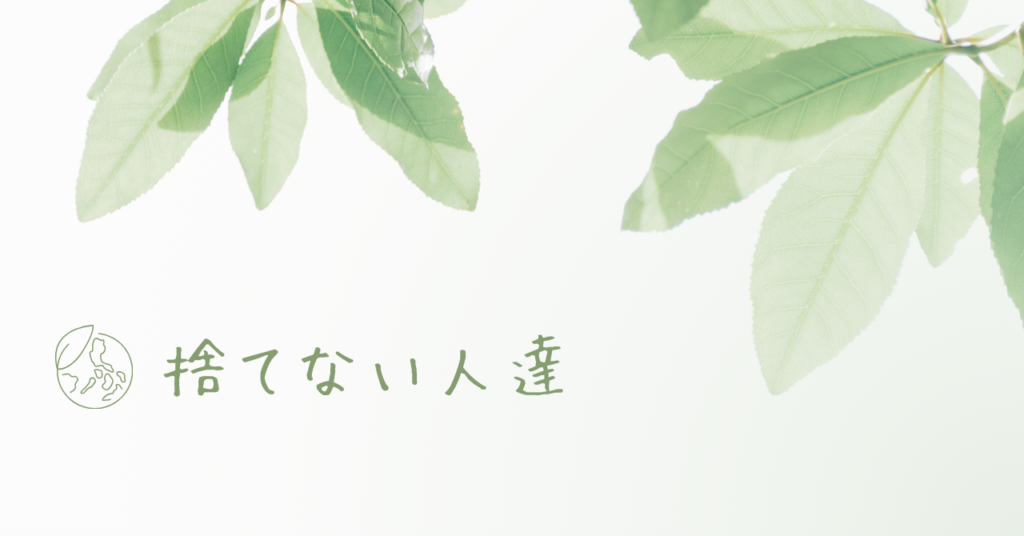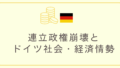ドイツに住んでいて、面白いなーと思うことは沢山あるのですが、その中の一つが、物を捨てない文化。街を歩いていてよく見かけるのが、「Zum Verschenken」(お譲りします)という札が貼ってある中古品。使わなくなった額縁や食器類、洋服、本、CDなど、これまで色々なものを道端で見かけました。

日本では、道端の不良品を自宅に持って帰るということに対して、「お金に困っていると思われそう」とか、あまり良いイメージを持たれないことが多いかと思います。ここドイツでは誰も全く気にしていません。むしろ、使えるものを捨てるなんて勿体ない、タダで手に入るならラッキー、という節約志向です。

私も綺麗な木製の写真立てとオーブン料理用のお皿を持って帰ったことがあります。別にお金に困っているわけではないので、買っても良かったのですが、捨てるには勿体ない綺麗さだったので、我が家に迎え入れました!
今日は、このほかにもドイツの捨てない文化あるあるを見ていきます!
その1 包装材・段ボール
個人的にこれまでで一番面白かったのは、プレゼントの包装材。私の義母は、何でも捨てないで取っておく人。私がこれまで贈った日本からのお土産やクリスマスプレゼントの箱、包装材を丁寧に箪笥の中にしまっています。一昨年の義母からクリスマスプレゼントをもらった際、私が以前義母に贈ったお菓子の箱の中にプレゼントが入っていました。自分が贈ったものが、また自分の手元に戻ってくるというのも不思議な気持ちですね(笑)
それから、小包を送る段ボールや引っ越し用の段ボールも使い回しのものが多いです。ドイツの引っ越し業者に段ボールをお願いすると、使い古しの段ボールが届きました。多分、新品の段ボールもお金を払えばもらえるとは思うのですが、スタンダードプランでは使い古しのものが来ることが多いようです。これも日本ではあまり考えられませんよね。
その2 ティッシュ
次に面白いのが、鼻をかむティッシュ。日本ではポケットティッシュで鼻をかんだら、基本的にはゴミ箱へポイ、ですよね。ドイツのティッシュは丈夫にできているからか、鼻をかんだ後、ポケットにしまって再利用してる人が多くいます。感覚的には、ハンカチで鼻をかんでいるような感じなのでしょうか…。個人的には鼻水のついたティッシュを洋服のポケットに入れるのは憚られるので、私は2つにはがして、それぞれ一回だけ使うようにしてますが、ここにも捨てない文化・お国柄が出てるのが興味深いです。
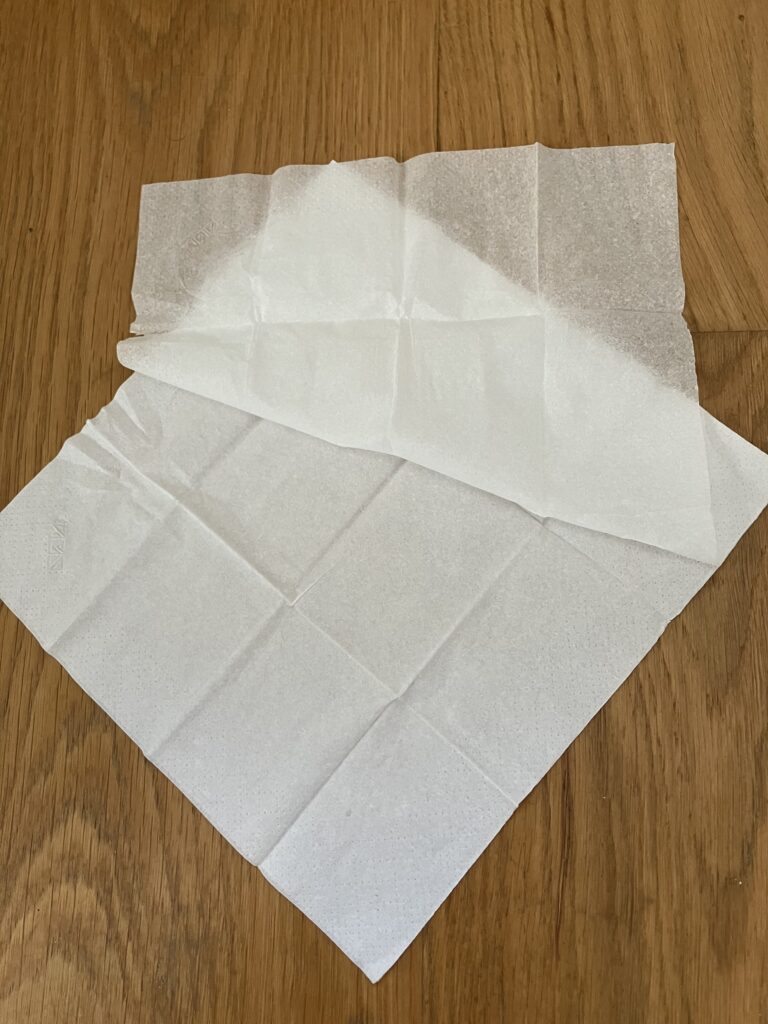
その3 食べきれなかった料理
捨てない文化その3はレストラン。食べきれない量のごはんが出てくることがあるドイツでは、残したご飯を持ち帰るのもOKです。日本は衛生上お断りするお店が多いと思いますが、ドイツではあくまで自己責任で、残飯を減らすために持ち帰る人が結構います。職場の人とピザを食べていた時に、半分くらい余っているピザを箱に詰めてもらって、「明日の朝ごはんに食べる」と言って持って帰っていたのを最初に見たときは、ちょっとびっくりしました。
まずは食べきれる分だけを注文することが大前提ですが、食べられるものを捨ててしまうのは確かに勿体ないので、理にかなった行動だなと感心しています。ちなみに、最近は、食糧廃棄の問題を解決するアプリToo Good To Goもあり、割安で食品を手に入れることで食品廃棄に貢献することもできるので、関心のある方は是非お試しあれ。私は残念ながらグルテンや乳製品などの食事制限が多いので、中身が指定できないこのアプリはまだ使ったことがないのですが、特にアレルギーや不耐症などの制限がない人であれば、お得にお買い物できる良いアプリだと思います。
その4 ジャムや蜂蜜のグラス
捨てない文化シリーズ、まだまだありますよ。お次はジャムや蜂蜜の入ったグラスの容器。ドイツでは手作りのジャムをプレゼントで頂くことがよくあります。グラスは洗って返してね、と言われることもあるし、自宅で別の食品を入れるために再利用することも。また、蜂蜜も地域の養蜂家のものを購入する場合、グラスを返納することがほとんど。洗浄して再利用するのが基本です。ドイツでは、プレスチックを減らすために、グラスの容器が食品に使われることが多いですが、グラスを使う場合も、壊れるまで再利用する人が多いように感じます。

この間、長距離電車に乗っている際に見てちょっと驚いたのは、トマトソースが入っていたと思われるグラスの瓶を水筒として利用している人がいたこと。水筒くらい買ったら良いのでは?と思ってしまった私ですが、エコの基準は人それぞれ。自分が心地よい方法を見つけるのが一番だと思います。
これからの暮らしのヒントになるかも?
文化の違いもあるので、全てを真似することはできないかもしれませんが、エコ生活のヒントになるのではないでしょうか?私は、あまりストイックに「捨てない文化」を実行するとストレスになってしまうので、ジャムの小瓶は洗って乾かして観葉植物を植えたり、保存容器として使ったり、綺麗な段ボールは保存して次の小包に使ったり、日本のお菓子の入った綺麗な箱を別の用途に使ったり、という簡単なものだけを実践しています。
何でも手に入る世の中ではありますが、物を大切に長く扱うことは、どの時代においても大事なことだと思います。私自身、過去には消費社会にどっぷり浸っていたこともあり、ドイツでの生活が自分の消費行動を見直す良いきっかけになっています。